家庭裁判所における教育的な働きかけ
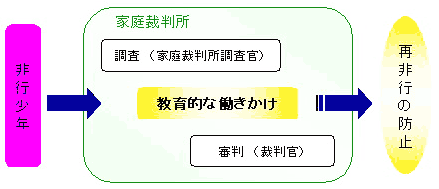
非行があった少年が再び非行に走ることのないようにするには、非行の内容や個々の少年の抱える問題に応じた適切な措置をとることが必要です。
家庭裁判所では、非行があった少年に対し、保護観察や少年院送致などの保護処分の決定や刑事処分とするための検察官送致の決定をしていますが、そのような処分までは行わない少年に対しても、非行について反省させ、これを繰り返すことのないように、調査から審判、処分の決定までの過程で、様々な方法で教育的な働きかけを行っています。
教育的な働きかけの例
調査では、それぞれの少年や保護者の問題に焦点を当てた指導を行います。保護者も同席させ、必要がある場合には、継続的に少年や保護者と面接し、より深く働きかけていくこともあります。また、審判の場では,裁判官が少年に、非行や生活態度を反省し、これを繰り返すことのないよう訓戒(くんかい)を与え、保護者に対する指導も行います。
被害者の方の視点を取り入れた講習
万引きをした少年などに対し、犯罪被害を受けた方の被害の実情や気持ちなどを聞かせ、「万引きくらいで」などと軽く考えがちな非行について反省を深めさせるための講習が行われています。
民間ボランティアへの補導の委託
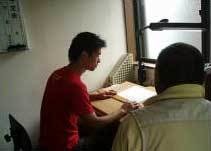
補導委託(模擬)
社会奉仕活動
少年を地域の清掃や老人福祉施設等における介護などの社会奉仕活動に参加させるといった方法の働きかけも行われています。例えば、少年を特別養護老人ホームに3日程度宿泊させたり、通わせたりして、お年寄りの話し相手や食事の介添え、車いすでの移動の補助をするなどの活動に参加させています。
わずかな期間でも、このような活動をする中で、少年は、社会に対する償いの気持ちを持つようになったり、お年寄りから感謝されたり頼られたりすると、自分も人の役に立てたという喜びを体験し、お年寄りが一生懸命頑張っている姿やそこで懸命に働いている職員の姿に心を打たれたりもします。その結果、社会や被害を受けた方のことを具体的に考え始めたり、駄目だと思っていた自分に自信を回復したり、思いやりの大切さを感じたりして、更生のきっかけをつかむことになります。
親子での共同作業の体験
親子関係の問題が非行の大きな原因になっている場合などに、親子で合宿などに参加させ、共同作業を通じて親子関係の調整を図ることもあります。
