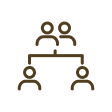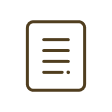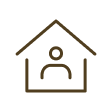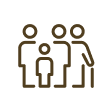裁判所を利用する


家事手続
家事審判
裁判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて裁判をする手続です。
家事調停
裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
離婚訴訟
離婚について家事調停で解決ができない場合の手続です。
その他
履行勧告や執行文付与、当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度などについて、ご案内しています。
- 夫婦関係調整調停(離婚)
- 離婚やそれに伴う財産分与、慰謝料、親権者の指定、年金分割の割合などについて話し合う手続です。
- 夫婦関係調整調停(円満)
- 夫婦の関係を円満にするために話し合う手続です。
- 内縁関係調整調停
- 内縁関係にある男女関係について解消することなどについて話し合う手続です。
- 婚姻費用の分担請求調停
- 夫婦の間で、生活費について話し合う手続です。
- 財産分与請求調停
- 離婚に伴う財産分与について話し合う手続(離婚後の場合)です。
- 年金分割の割合を定める調停
- 離婚に伴う年金分割の分割割合について話し合う手続(離婚後の場合)です。
- 慰謝料請求調停
- 不貞等の行為や、相手の行為が原因の離婚に対する慰謝料について話し合うための手続です。
- 離婚後の紛争調整調停
- 離婚後に生じた紛争について話し合うための手続です。
- 協議離婚無効確認調停
- 協議離婚届を勝手に出された場合に、これを回復するための手続です。
- 親権者変更調停
- 離婚後に、親権者の変更について話し合う手続です。
- 養育費請求調停
- 離婚後の養育費について話し合う手続です。
- 面会交流調停
- 子どもとの面会交流について話し合う手続です。
- 子の監護者の指定調停
- 離婚した夫婦の間や別居中の夫婦の間で、子の監護者について話し合う手続です。
- 子の引渡し調停
- 親権者でない親が子どもを連れ去った場合など、親権者に対する子どもの引渡しについて話し合う手続です。
- 親子関係不存在確認調停
- 婚姻中や離婚後一定期間内に生まれた子について、母の(元)夫の子ではないことを確認するための手続です(嫡出推定が及ばない子の場合)。
- 嫡出否認調停
- 婚姻中や離婚後一定期間内に生まれた子について、母の(元)夫の子ではないことを確認するための手続です。
- 認知調停
- 実の父に認知を求めるための手続です。
- 離縁調停
- 養親と養子の離縁について話し合うための手続です。
- 遺産分割調停
- 遺産の分割について相続人間で話し合う手続です。
- 寄与分を定める処分調停
- 遺産分割の際に、亡くなった人の財産の維持又は増加について特別に寄与した相続人の寄与分について話し合う手続です。
- 特別の寄与に関する処分調停
- 亡くなった人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした、相続人ではない亡くなった人の親族の寄与について話し合う手続です。
- 遺留分減殺による物件返還請求調停
(令和元年7月1日より前に開始した相続に限る) - 遺産相続において贈与や遺贈のために受け取る相続財産の割合が法定の最低限度を下回った場合に、その回復について話し合う手続です。
- 遺留分侵害額の請求調停
(令和元年7月1日以降に開始した相続に限る) - 遺産相続において贈与や遺贈のために受け取る相続財産の割合が法定の最低限度を下回った場合に、その回復について話し合う手続です。
- 遺産に関する紛争調整調停
- 相続人間において、遺産の有無、範囲、権利関係等の争いがある場合にそれを話し合う手続です。
- 後見ポータルサイト
- 成年後見制度を利用するために必要な情報をまとめてご案内しているサイトです。
初めて成年後見制度を利用する方(初めて後見・保佐・補助開始の申立て、任意後見監督人選任の申立てをする方)は、まずは本サイトをご覧ください。
- 後見開始
- 認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が欠けているのが通常の状態の方を保護するための手続です。
- 保佐開始
- 認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が著しく不十分な方を保護するための手続です。
- 補助開始
- 認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を保護するための手続です。
- 任意後見監督人選任
- 本人があらかじめ結んでいた任意後見契約について任意後見監督人を選任するための手続です。
- 成年後見人(保佐人、補助人)の選任
- 成年後見人(保佐人、補助人)を選任するための手続です。
(初めて選任する場合は、後見・保佐・補助の開始の審判になります。)
- 成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)の選任
- 成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)を選任するための手続です。
- 辞任についての許可(成年後見制度)
- 1.成年後見人(保佐人、補助人)
2.監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人)
を辞任するための手続です。
- 成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産の処分についての許可
- 成年後見人(保佐人、補助人)が成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産を処分するための手続です。
- 成年被後見人(被保佐人、被補助人)に関する特別代理人(臨時保佐人・臨時補助人)の選任
- 成年後見人(保佐人、補助人)と成年被後見人(被保佐人、被補助人)との利益が相反する場合に特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)を選任するための手続です。
- 報酬の付与(成年後見制度)
- 成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人が成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人の財産の中から報酬を受けるための手続です。
- 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(回送)の嘱託
- 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(回送)を受けるための手続です。
- 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(回送)の嘱託の取消し・変更
- 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(回送)嘱託の審判の取消し又は変更のための手続です。
- 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
- 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為をするための手続です。
- 後見ポータルサイト
- 未成年後見制度を利用するために必要な情報をまとめてご案内しているサイトです。
初めて未成年後見人選任の申立てをする方は、まずは本サイトをご覧ください。
- 未成年後見人選任
- 親権を行う者がない場合に未成年後見人を選任するための手続です。
- 未成年後見人選任(未成年後見人が欠けた場合や追加の選任が必要な場合)
- 未成年後見人が欠けた場合や追加の選任が必要な場合に、未成年後見人を選任するための手続です。(親権を行う者がない場合に未成年後見人を選任する場合は、上記の「未成年後見人選任」になります。)
- 未成年後見監督人選任
- 未成年後見監督人を選任するための手続です。
- 辞任についての許可(未成年後見制度)
- 未成年後見人、未成年後見監督人を辞任するための手続です。
- 特別代理人選任(未成年後見人と未成年者との利益相反の場合)
- 未成年後見人と未成年者との利益が相反する場合に特別代理人を選任するための手続です。
※「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」のページに遷移します
- 報酬の付与(未成年後見制度)
- 未成年後見人、未成年後見監督人が未成年者の財産の中から報酬を受けるための手続です。
- 不在者財産管理人選任
- 行方不明になった人に財産がある場合にその財産を管理する不在者財産管理人を選任するための手続です。
- 不在者の財産管理人の権限外行為許可
- 不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分する(民法第103条に定められた権限を越える行為をする)ための手続です。
- 失踪宣告
- 行方不明になって死亡していると思われる人に関する手続です。
- 子の氏の変更許可
- 両親が離婚した後などに、子どもの氏(子どもの戸籍)を親権者の氏に変更するための手続です。
- 養子縁組許可
- 未成年者を養子にするための手続です。
- 死後離縁許可
- 養親(又は養子)が死亡した場合の離縁の手続です。
- 特別養子適格の確認・特別養子縁組成立
- 特別養子縁組をするための手続です(特別養子縁組が成立すると、養子となる者とその実親側との親族関係は消滅します)。
- 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)
- 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する場合に特別代理人を選任する手続です。
- 親権者変更(親権者行方不明(死亡)等の場合)
- 親権者が行方不明(死亡)等の場合に、親権者を他の一方に変更するための手続です。
- 相続の放棄の申述
- 相続人が亡くなった人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がないようにするための手続です。
- 相続の限定承認の申述
- 相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった人の債務の負担を受け継ぐ手続です。
- 相続の承認又は放棄の期間の伸長
- 相続人が亡くなった人の相続について承認又は放棄をする期間を伸長するための手続です。
- 相続財産清算人の選任
- 相続人がいない場合に、相続財産を清算するための手続です。
- 特別縁故者に対する相続財産分与
- 相続財産清算人が選任されている場合に、相続人でない人で特別な縁故関係にあった人が、相続財産を得るための手続です。
- 遺言書の検認
- 遺言者が自分で書いた「遺言書」を持っている人が遺言者の死亡後にしなければならない手続です。
- 遺言執行者の選任
- 遺言の内容を実現するための「執行者」を選任するための手続です。
- 遺留分放棄の許可
- 相続人が、亡くなった人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分(遺留分)を、相続の開始前に放棄するための手続です。
- 遺留分の算定に係る合意の許可
- 一定の要件を満たす中小企業の後継者が、遺留分の算定についてなされた合意の許可を求める手続です。
- 保護者選任
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律で定められた「保護者」を選任するための手続です。
- 保護者の順位の変更及び選任
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律で定められた「保護者」の順位の変更及び選任するための手続です。
- 医療観察法における保護者選任のための扶養義務者の指定
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する対象者に扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)が存在しないか又は扶養義務者が保護者になることができないような場合に、扶養義務者を指定する手続です。
- 子の氏の変更許可
- 両親が離婚した後などに、子どもの氏(子どもの戸籍)を親権者の氏に変更するための手続です。
- 氏の変更許可
- 戸籍上の氏名のうち、「氏」について変更するための手続です。
- 氏の振り仮名の変更許可
- 戸籍上の氏名のうち、「氏の振り仮名」について変更するための手続です。
- 名の変更許可
- 戸籍上の氏名のうち、「名」について変更するための手続です。
- 名の振り仮名の変更許可
- 戸籍上の氏名のうち、「名の振り仮名」について変更するための手続です。
- 戸籍訂正許可
- 戸籍の記載に誤記等がある場合にこれを訂正するための手続です。
- 性別の取扱いの変更
- 性別の取扱いを男(女)から女(男)に変更するための手続です。
- 履行勧告
- 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、取決めを守るように勧告する手続です。
- 間接強制
- 一定の債務を履行しない義務者に対し、間接強制金を課すことを警告し、自発的な履行を促すための手続です。
- 執行文付与
- 執行文付与の申立手続です。
- 即時抗告
- 審判に対する不服(即時抗告)の申立てをする手続です。
- 子の引渡しの強制執行
- 債務者(義務者)が、債権者(権利者)に対して任意に子を引き渡さない場合に利用することができる強制執行の手続です。
- 無戸籍の方に関する手続
- 何らかの事情で出生届が提出されずに「無戸籍」の状態になっている方について戸籍を作るための手続です。
- 当事者に対する住所等の秘匿制度
- やむを得ず反対当事者に知られては困る情報が書面に現れる場合に利用することができる制度です。
民事手続
民事訴訟
主として財産権に関する紛争を、裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりした後に、判決によって紛争の解決を図る手続です。
民事調停
裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
その他
主として財産権に関する紛争を、裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりした後に、判決によって紛争の解決を図る手続です。
- 担保不動産競売
- 債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、担保権を実行して当該不動産を売却して債権を回収する手続です。
※担保権は、債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。
- 強制競売
- 判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者が所有している不動産を、裁判所が差し押さえて、売却し、売却代金を債権者に分配することにより債権を回収する手続です。
- 担保不動産収益執行
- 債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、担保権の対象である不動産から生ずる収益(賃料等)から債権を回収する手続です。
※担保権は、債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。
- 形式的競売
- 複数人が共有する不動産について、判決などで競売を命じられた場合に利用する手続です。
※この手続は、債権の回収を目的とする手続ではありません。
- 自動車競売
- 判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者が所有している自動車を、裁判所が差し押さえて、売却し、売却代金を債権者に分配することにより債権を回収する手続です。
- 債権執行(債務名義に基づく差押え)
- 判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者の給与や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。
- 債権執行(養育費等に基づく差押え)
- 調停調書や公正証書などで取り決めた養育費や婚姻費用の分担金等が支払われない場合に、債務者の給料や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。一般の債権執行手続に比べて、差し押さえることのできる債務者の給与等の範囲が拡大されています。
- 債権執行(抵当権に基づく物上代位としての賃料差押え)
- 債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、その不動産の賃料などを差し押さえ、債権を回収する手続です。
※担保権は、債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。
- 財産開示
- 債務者の財産がどこにあるかわからない場合等に、債務者の財産に関する情報を得るため、債務者(開示義務者)に裁判所に出頭してもらい、財産の状況について陳述してもらう手続です。この手続の結果を踏まえて、債権執行や不動産の強制競売などを申し立てるかを検討することができます。
- 情報取得
- 債務者の銀行預金や給与、不動産等に関する情報を、債権者が特定した銀行や市町村、登記所等から提供してもらう手続です。
この手続の結果を踏まえて、債権執行や不動産の強制競売などを申し立てるかを検討することができます。
- 動産執行
- 判決などの債務名義に基づいて債務者の動産を差し押さえ、当該動産を売却して債権の満足を得る手続です。
- 不動産引渡(明渡)執行
- 判決などの債務名義に基づいて債務者の不動産に対する占有を解いて、債権者にその占有を取得させる手続です。
- 破産
- 裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に分配(配当)する手続です。
- 通常再生
- 経済的に苦しい状況にある法人や個人(債務者)が、自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除され、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。
- 個人再生
- 個人債務者のみを利用対象者とする民事再生です。利用には一定の要件がありますが、通常再生と比べると、手続や費用等について関係者の負担が軽くなっています。
- 会社更生・特別清算
- 会社更生
経済的に窮境にある株式会社について、裁判所が選任した更生管財人のもと、更生計画を策定しその計画を遂行して、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、当該会社の事業の維持更生を図る手続です。
特別清算
解散後清算中の株式会社について、当該会社を清算するのが非常に難しい状況にある場合又は債務超過(当該会社の負債総額がその資産総額を上回っている状態)の疑いがある場合に、裁判所の命令により開始され、その監督の下で行われる特別の清算手続です。