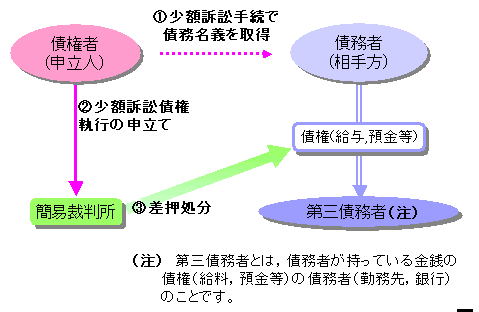- どこの簡易裁判所に訴訟を起こせばいいですか?
- 訴訟は、原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に起こします。例えば、相手方の住所が東京23区内にある場合には、東京簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。相手方の住所が分からない場合には、分かっている最後の住所地を管轄する簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。ただし、事件の種類によっては、それ以外の簡易裁判所(例えば、金銭請求の場合には、支払をすべき場所の簡易裁判所、不動産に関する請求の場合には、その不動産所在地の簡易裁判所)にも、訴訟を起こすことができます。
申立先を調べたい方は「申立書提出先一覧(簡易裁判所) 」 をご覧ください。
- どこの簡易裁判所に調停の申立てをすればいいですか?
- 調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。例えば、相手方の住所が東京23区内にある場合には、東京簡易裁判所に申し立てることになります。
申立先を調べたい方は「申立書提出先一覧 (簡易裁判所)」をご覧ください。
- どこの簡易裁判所に支払督促の申立てをすればいいですか?
- 支払督促は、原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。例えば、相手方の住所が東京23区内にある場合には、東京簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てることになります。ただし、コンピュータ処理による支払督促については例外もあります。
申立先を調べたい方は「申立書提出先一覧(簡易裁判所) 」をご覧ください。
- 主な紛争の種類と裁判手続の対応はどうなっていますか?
- 主な紛争の種類と裁判手続の一覧表は次のとおりです。
※少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限ります。
主な紛争の種類と裁判手続の一覧表
| 紛争の種類 |
支払督促 |
調停 |
訴訟 |
※少額訴訟 |
| 貸金、立替金 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 売買代金 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 給料、報酬 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 請負代金、修理代金 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 家賃、地代の不払 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 敷金、保証金の返還 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 損害賠償(交通事故ほか) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 家賃、地代の改定 |
|
〇 |
〇 |
|
| 建物、部屋の明渡し |
|
〇 |
〇 |
|
| 土地、建物の登記 |
|
〇 |
〇 |
|
- 訴訟の相手方になった場合はどうすればいいですか?
- 訴訟とは、当事者間に紛争がある場合に、裁判官が双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして、判決によって解決を図る手続です。
民事訴訟では、訴訟を起こす方を原告と、その相手方を被告と呼びます。被告とは、民事訴訟の相手方を指す用語で、犯罪の疑いを掛けられている刑事事件の被告人とは違う意味で用いられています。被告になった場合には、裁判所から訴状と最初の期日の呼出状が送られますので、それらをよく読んでください。そして、訴状に対する言い分をあらかじめ答弁書(訴状に書いてある原告の請求、主張等に被告が返答する書面)に書いて提出しておくと、あなたの言い分を正確に裁判所と原告に伝えることができます。
また、最初の期日には、自分の言い分を裁判官に詳しく説明できるように準備し、あなたの言い分を説明するのに役に立つ証拠書類は、必ず持参してください。
なお、訴訟の途中でも、相手方が話合いに応ずれば、裁判所で話合いをして紛争を解決することもできます。これを和解といいます。和解を希望される方は、裁判所に申し出てください。
被告が決められた最初の期日に出頭せず、答弁書等において原告の請求を争う意図を明らかにしていない限り、原告の請求どおりの判決が出ることがありますので、御注意ください。
- 期日にどうしても裁判所に出向けない場合はどうしたらいいですか?
- 決められた期日に、病気などの理由で裁判所に来られない場合には、簡易裁判所の担当の裁判所書記官に御相談ください。やむを得ない場合には、期日を変更することもあります。その場合には、事情を証明する診断書などの書類を提出していただくことがあります。原則として、仕事の都合だけで期日を変更することはできませんから、御注意ください。
なお、被告が答弁書を提出せず、決められた最初の期日にも裁判所に来ないと、原告の言い分どおりの判決が出ることがありますので、御注意ください。
- 判決にはどのような効力がありますか?
- 判決は、判決送達日から2週間以内に不服を申し立てなければ、確定します。確定すると、判決の内容を争うことができなくなります。訴訟を起こした方、つまり原告の言い分が認められた判決が確定したにもかかわらず、相手方、つまり被告が判決に従わない場合には、原告は、判決の内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。また、判決に「この判決は、仮に執行することができる」と記載されている場合には、判決が確定しなくても、直ちに判決の内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。ただし、被告が不服を申し立てると、その強制執行手続が停止されることもあります。
- 判決に不服がある場合はどうしたらいいですか?
- 原告と被告は、いずれも、判決に不服がある場合には、地方裁判所に不服の申立てをすることができます。この申立てを控訴といいます。控訴ができる期間は、判決送達日から2週間以内です。2週間以内に控訴の手続をとらないと、判決は確定します。確定すると判決の内容を争えなくなりますから、注意してください。控訴をする場合には、控訴状という書面を提出してください。控訴状は、判決をした簡易裁判所のある地区の裁判を受け持つ地方裁判所あてにして、判決を受けた簡易裁判所に提出することになります。
なお、少額訴訟手続の判決に対しては、同じ簡易裁判所に異議の申立てをすることができるだけで、地方裁判所に控訴をすることはできません。
- 判決が控訴されずに確定した後の手続はどうなりますか?
- 判決送達日から2週間経過すると、控訴をすることができなくなり、判決は確定します。判決が確定すると、それ以降は判決の内容を争うことができなくなります。
被告に対して金銭の支払など一定の行為を命ずる判決が確定した場合には、被告は、命ぜられた行為をしなければなりません。被告がこれに応じない場合には、原告は、判決の内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。
- 和解した後の手続はどうなりますか?
- 和解とは、訴訟の途中で話合いをして紛争を解決することをいいます。和解をすると、裁判所書記官がその内容を記載した和解調書を作ります。
和解調書の効力は、確定した判決と同じです。
- 少額訴訟手続とはどのような手続ですか?
- 少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決を図る手続です。市民間の規模の小さな紛争を少ない時間と費用で迅速に解決することを目的として、作られた手続です。少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を起こすときに、原告がそのことを希望し、相手方である被告がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。少額訴訟手続の審理では、最初の期日までに、自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出してもらうことになっています。また、証拠は、最初の期日にすぐ調べることができるものに制限されています。ですから、紛争の内容が複雑であったり、調べる証人が多く1回の審理で終わらないことが予想される事件は、裁判所の判断で通常の手続により審理される場合があります。
少額訴訟手続でも、話合いで解決したいときには、和解という方法があります。話合いによる解決の見込みがない場合には、原則として、その日のうちに判決の言渡しをすることになっています。少額訴訟の判決は、通常の民事裁判のように、原告の言い分を認めるかどうかを判断するだけでなく、一定の条件のもとに分割払、支払猶予、訴え提起後の遅延損害金の支払免除などを命ずることができます。
少額訴訟手続の判決に対しては、同じ簡易裁判所に異議の申立てをすることができますが、地方裁判所に控訴をすることはできません。
なお、少額訴訟手続の利用回数は、1人につき同じ裁判所に年間10回までと制限されています。
- 少額訴訟の相手方になった場合はどうすればいいですか?
- 原告は、あなたを被告として、少額訴訟手続による審理を求める訴訟を起こしました。あなたには、裁判所から訴状、口頭弁論期日呼出状、少額訴訟手続の内容を説明した書面等が送られたことと思いますが、それらの書面をよく読んでください。
少額訴訟手続は、特別の事情がある場合を除き、最初の期日において、当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして一回の期日で審理を終え、直ちに判決を言い渡すのを原則としています。あなたが、このような、少額訴訟手続による審理を希望しない場合には、簡易裁判所の通常の手続による審理を求めることができます。その場合には、最初の期日において弁論をするまでに、訴訟を通常の手続へ移行させる旨の申し出をしなければなりません。なお、少額訴訟では反訴を提起することはできません。
少額訴訟手続の概要については、「少額訴訟手続とはどのような手続ですか?」を御覧ください。
あなたが、少額訴訟手続による審理に異議がない場合には、最初の期日の前までに答弁書を提出しておくと、自分の言い分を裁判所と原告に正確に伝えることができます。
あなたに届いた口頭弁論期日呼出状には、裁判が行われる期日が書いてありますので、その期日に、呼出状に記載された法廷に出席してください。
どうしても決められた期日に出席できない場合には、担当の裁判所書記官に御相談ください。なお、あなたが答弁書を提出しないまま、決められた裁判の期日に出席しない場合には、原告の言い分どおりの少額訴訟判決が出ることがありますので、御注意ください。
- 少額訴訟の手続の流れはどうなりますか?
- 少額訴訟手続による審理を求める訴状が裁判所で受け付けられると、最初の期日が決められ、当事者双方にその通知がされます。訴えられた相手方には、訴状の副本と一緒に口頭弁論期日呼出状、少額訴訟手続の内容を説明した書面、答弁書用紙、事情説明書といった書面が同封されていますから、まず、少額訴訟手続の内容を説明した書面をよく読んでください。その上で、相手方は答弁書で自分の言い分を書いて反論することができます。また、事情説明書は、少額訴訟手続により、原則として、最初の期日に裁判が終わるよう、双方から裁判所に対し、事前に必要な事情を伝えてもらう書面です。
次に、裁判の前に準備することを御説明します。
少額訴訟では、裁判所が最初の期日に当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして判決をします。訴訟では、双方の言い分に食い違いがある場合、証拠に基づいてどちらの言い分が正しいかを判断することになりますから、自分の言い分の裏付けになる証拠は、最初の期日に提出できるように準備してください。
主な証拠としては、契約書、領収書、覚書のほか、交通事故の場合の事故証明などの証拠書類や、人証といって証人や当事者本人などの供述があります。 また、判決以外にも、訴訟の途中で裁判所で話合いをして、相手方との間で分割払の約束をするなど、和解の方法により解決することもできます。
最後に、期日にどうしても裁判所に出向けない場合については、「期日にどうしても裁判所に出向けない場合はどうしたらいいですか?」を御覧ください。
- 少額訴訟終了後の手続はどうなりますか?
- 少額訴訟判決は、当事者が判決送達日から2週間以内に異議を申し立てなければ、確定します。確定すると、判決の内容を争うことができなくなります。少額訴訟を起こした方、つまり原告の言い分が認められた少額訴訟判決には、「この判決は、仮に執行することができる」旨の仮執行宣言が付されますので、相手方つまり被告が判決に従わない場合には、原告は、判決確定前であっても、少額訴訟判決の内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。ただし、被告が異議を申し立てるとともに、強制執行停止手続を求めた場合には、その強制執行手続が停止されることがあります。
少額訴訟判決に不服がある場合の手続について御説明します。
原告と被告は、いずれも少額訴訟判決に不服がある場合には、少額訴訟判決をした簡易裁判所に異議の申立てをすることができます。なお、少額訴訟の判決に付された支払猶予、分割払、期限の利益の喪失、訴え提起後の遅延損害金の支払義務の免除の定めに関する裁判に対しては異議を申し立てることはできません。 異議後の審理は、少額訴訟の判決をした裁判所と同一の簡易裁判所において、通常の手続により審理及び裁判をすることになりますが、異議後の訴訟においても反訴を提起することはできませんし、異議後の訴訟の判決に対しては控訴をすることができないなどの制限があります。
なお、少額訴訟手続及び異議後の訴訟の手続においても、訴訟の途中で話合いをして和解により紛争を解決することができます。和解が成立すると、裁判所書記官がその内容を記載した和解調書を作ります。和解調書の効力は確定した判決と同じです。
- 少額訴訟債権執行とはどのような手続ですか?
- 少額訴訟債権執行とは、簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義(判決、和解調書等)を得たときに限り、その簡易裁判所において行う金銭債権(給料、預金等)に対する強制執行のことです。
- 調停の相手方になった場合はどうしたらいいですか?
- 調停は、裁判官と一般の方から選ばれた調停委員が申立人と相手方の間に入り、話合いで円満に紛争を解決する手続です。話合いを進めるためには、裁判所から通知された日時に必ずおいでいただかなければなりません。病気などのためにどうしてもおいでになれない場合には、簡易裁判所の担当の裁判所書記官に御相談ください。
次に、調停の前に準備することについて御説明します。
調停期日で紛争の内容やあなたの言い分について説明できるように準備しておいてください。契約書や領収書など紛争の内容を説明するために役に立つ書類がありましたら、当日持参するようにしてください。
- 期日にどうしても裁判所に出向けない場合はどうしたらいいですか?
- 調停は、話合いにより紛争を解決する手続です。したがって、調停の相手方になった場合には、通知された日時に、必ずおいでいただかなければなりません。もし、病気などのためにどうしてもおいでになれない場合には、簡易裁判所の担当の裁判所書記官に御相談ください。やむを得ない場合には、御家族や会社の従業員などを代理人にすることができる場合もあります。また、期日を変更することもあります。
- 調停が成立した場合の効果はどうなりますか?
- 話合いがまとまると、裁判所書記官がその内容を調書に記載して、調停が成立します。この調書には、確定した判決と同じ効力がありますので、原則として、後から不服を述べることはできません。この調書において、金銭の支払や建物の明渡しなど一定の行為をすることを約束した場合には、当事者はこれを守る必要があります。もし一方がその約束した行為をしない場合には、もう一方は、調停の内容を実現するため、強制執行を申し立てることができる場合があります。
調停調書を受け取るためには、簡易裁判所に申請していただく必要があります。
- 調停が成立しなかった場合のその後の手続はどうすればいいですか?
- 調停では、お互いの意見が折り合わず、話合いの見込みがない場合には、手続を打ち切ります。また、話合いの見込みがない場合には、裁判所は、適切と思われる解決案を示すこともあります。これを「調停に代わる決定」といいます。この決定は、お互いが納得すれば調停が成立したのと同じ効果がありますが、どちらかが2週間以内に異議を申し立てると、効力を失い、調停は成立しなかったことになります。
調停が成立しなかった場合に、紛争の解決をなお希望されるのであれば、訴訟を起こすことができます。訴訟は、紛争の対象となっている金額が、140万円以下の場合には簡易裁判所に、140万円を超える場合には地方裁判所に起こします。調停打切りの通知を受けてから2週間以内に同じ紛争について訴訟を起こしますと、調停申立ての際に納めた手数料の額は、訴訟の手数料の額から差し引くことができます。
- 調停に代わる決定とはどのような手続ですか?
- 調停では、お互いの意見が折り合わず、話合いの見込みがない場合には、手続を打ち切りますが、裁判所が適切と思われる解決案を示すこともあります。これを「調停に代わる決定」といいます。この決定は、お互いが納得すれば調停が成立したのと同じ効果がありますが、どちらかが2週間以内に異議を申し立てると、効力を失います。その場合には、訴訟を起こすことができます。
- 特定調停とはどのような手続ですか?
- 特定調停は、個人・法人を問わず、このままでは返済を続けていくことが難しい方が、債権者と返済方法などについて話し合って、生活や事業の建て直しを図るための手続として、民事調停の特例として定められたものです。
調停の申立てがあると話合いの期日が指定されます。この期日では、調停委員が、申立人から、生活や事業の状況、これからの返済方法などについて聴き、相手方の考えを聴いた上で、残っている債務をどのように支払っていくことが、公正かつ妥当であり、また経済的に合理的なのかについて、裁判所が双方の意見を調整していきます。したがって、特定調停で成立した合意の内容は、実質的に公平で、法律などに違反するものでなく、債務者の生活や事業の建て直しのために適切なものであって、しかも、そのような内容の合意をすることが当事者双方にとって経済的に合理的なものとなります。
なお、特定調停手続の進め方は、通常の調停と基本的には同じですから、調停手続についての他の質問も御参照ください。
- 特定調停を申し立てるにはどうしたらいいですか?
- 特定調停を申し立てるには、調停申立書という書面を、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出してください。そのときには、特定調停の手続を利用したいことを明らかにしてください。また、毎月、どれくらいの額なら支払えるのか、期限をどのくらい猶予してもらいたいのかも示してください。
また、事業者が申し立てる場合には、債権者などとの交渉の経過についても明らかにしてください。会社などの法人が申し立てる場合には、労働組合の名称や所在地、代表者名、連絡先なども明らかにしてください。
そのほか、調停を申し立てるための手数料として、法律で定められた金額を納めることなどが必要となります。
- 特定調停の申立ての時にどのような資料が必要ですか?
- 特定調停を申し立てるときには、このままでは返済を続けていくことが難しいということを明らかにする資料として、資産の一覧表、債権者及び担保権者の一覧表、生活や事業の状況が分かるもの、借入れの内容やこれまでの返済の内容が分かるものなどを提出してください。
例えば、生活の状況が分かるものとしては、給与明細、家計簿、通帳などの写しが、事業の内容が分かるものとしては、貸借対照表、損益計算書、資金繰表、事業計画書、会計帳簿などの写しが考えられます。また、借入れの内容が分かるものとしては、契約書などの写しが、これまでの返済の内容が分かるものとしては、領収証などの写しが考えられます。
なお、資産としては、不動産、自動車、預貯金、生命保険解約返戻金、事業用の機械、売掛金、手形債権などが考えられます。
このほかにも、裁判所から必要な書類を指示された場合には、その指示に従ってください。
- 支払督促の申立書を提出した後の手続の流れはどうなりますか?
- 支払督促が申し立てられると、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促を発付します。しかし、相手方が異議を申し立てると、事件は、通常の訴訟手続で審理されることになります。相手方が支払督促を受け取ってから異議を申し立てずに2週間を経過した場合には、申立人は、それから30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。仮執行宣言の申立てをすると、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促に仮執行宣言を付します。仮執行宣言が付されると、申立人は、直ちに強制執行手続をとることができます。申立人が30日以内に仮執行宣言の申立てをしなかった場合には、支払督促は効力を失います。
仮執行宣言の付された支払督促に対し、相手方が異議を申し立てた場合には、事件は、通常の訴訟手続で審理されることになります。仮執行宣言の付された支払督促に対し、相手方が異議を申し立てることのできる期間は、仮執行宣言付支払督促を受け取ってから2週間以内です。
- 支払督促を受けた場合はどうしたらいいですか?
- 支払督促は、申立人の申立内容だけを審査して、相手方に金銭の支払を命ずるものです。申立人の請求金額は「請求の趣旨」の欄に、申立人の言い分は「請求の原因」の欄に書かれています。この支払督促に不服があれば、異議を申し立てることができます。
異議を申し立てる場合には、支払督促に同封されている「異議申立書」という書面に所定の事項を書いて、支払督促を出した簡易裁判所に郵送するか、直接持参するかしてください。異議を申し立てると、事件は、通常の訴訟手続で審理されることになります。
支払督促送達日から2週間以内に異議の申立てをしないと、支払督促に仮執行宣言が付されることがあります。仮執行宣言が付されると、直ちに強制執行を受けることがあります。
なお、支払督促に対する異議の申立期間は、支払督促に仮執行宣言が付されるまでです。また、仮執行宣言の付された支払督促に対する異議の申立期間は、仮執行宣言の付された支払督促送達日から2週間以内です。
- 仮執行宣言付支払督促を受けた場合はどうすればいいですか?
- 支払督促は、申立人の申立内容だけを審査して、相手方に金銭の支払を命ずるものです。支払督促に仮執行宣言が付されると、申立人は、直ちに強制執行手続をとることができます。この支払督促に不服があれば、異議を申し立てることができます。その期間は、仮執行宣言付支払督促送達日から2週間以内です。異議を申し立てる場合には、支払督促に同封されている「異議申立書」という書面に所定の事項を書いて、支払督促を出した簡易裁判所に郵送するか、直接持参するかしてください。
なお、仮執行宣言の付されている支払督促に異議を申し立てても、執行停止の手続をとらなければ、強制執行を停止することはできません。
異議を申し立てると、事件は、通常の訴訟手続で審理されることになります。異議の申立てをしないと、仮執行宣言付支払督促の内容について、今後争うことができなくなります。