第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況
裁判官の人事評価の在り方について検討するに当たっては,裁判官の人事評価の現状と裁判官人事の概況について把握しておくことが必要である。この点に関し,当研究会において幹事からされた説明は,以下のとおりである。
1. 裁判官数等
裁判官の定員は,最高裁判所長官,最高裁判所判事,高等裁判所長官を除き,判事1445名,判事補820名,簡易裁判所判事806名,合計3071名で ある(平成14年7月現在)。実員は,退官等による減員と新規任命により一年を通じて変動するが,実員が最も増加し定員を充足又はこれに近い状態になるの は,判事は判事補が判事に任命される4月,判事補は司法修習生からの新規任命が行われる10月,簡易裁判所判事は簡易裁判所判事選考委員会による選考に合格した者(いわゆる特任簡判)が新たに任命される8月である。
裁判官の一部は,最高裁判所調査官,事務総局局課長,局付,研修所教官等に充てられているが,その余は,事件数等を基準として定められた配置定員に従って,全国の高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所に配置されている。高等裁判所は8庁(支部が6),地方裁判 所・家庭裁判所は本庁が各50庁(支部が各203),簡易裁判所は地方裁判所本庁・支部と併設されていないいわゆる独立簡易裁判所を含めて438庁である。ただし,事件数が著しく少ない一部の地方裁判所・家庭裁判所の支部,独立簡易裁判所には,裁判官が常駐していない。
なお,裁判官から法務省等の行政省庁へ出向する場合は,検事に転官しているので,裁判官定員の枠外である。
2. 判事の担当職務等
判事のほとんどは,判事補として10年の経験を積んだいわゆるキャリア裁判官である。判事任命後しばらくは,地方裁判所・家庭裁判所の合議事件の陪席裁判官(同時に単独事件を担当するのが普通),高等裁判所の陪席裁判官,地方裁判所・家庭裁判所の中小規模支部の支部長等を務めるのが一般的である。地方裁判所・家庭裁判所の部総括(司法行政上は部の事務の取りまとめに当たり,裁判においては合議体の裁判長となる。その数は300余り。)に指名されるのが,大体,判事任命後10年目前後くらいから(東京地方裁判所では,現在,最も若い部総括が判事任命後12年目。地方ではこ れより早く部総括になる例もある。),所長への任命は,判事任命後20年経過後くらいから,高等裁判所部総括も経験年数はほぼ所長に準じるが,所長を経て任命される例が多い。
3. 判事補の担当職務等
司法修習生を終了して判事補に任命された者は,最初の2年半,東京,大阪を始めとする比較的規模の大きな地方裁判所に配置され,主として合議事件の陪席裁判官を務める。その後,多くの者は全国の地方裁判所・家庭裁判所に異動し,3年間,合議事件の陪席裁判官を務める傍ら,保全,執行等の決定事件,家庭裁判所の少年事件等の処理に当たる。判事補経験3年で簡易裁判所判事任命資格を取得するので,簡易裁判所の事件を担当する者もいる。この間,外国留学する者,民間企業に研修派遣される者,検事に転官して行政省庁に出向する者,事務総局の局付等になる者等がいる。
5年経過するといわゆる職権特例判事補の指名を受けて判事と同一の権限行使が可能になるが,現実に地方裁判所の訴訟事件を単独で担当するかどうかは,配置された裁判所の裁判官の構成にもよる。特例判事補の期間には,行政省庁へ出向する者,局付になる者等がいるほか,少数ながら高等裁判所の職務代行を命じられて,控訴事件の陪席裁判官を経験する者もいる。
なお,判事補については,任命直後,最初の転勤直前の3年目,職権特例指名後の6年目に,全員を対象に司法研修所で研修が実施されている。
4. 異動の実情
(1) 異動の必要性
5年経過するといわゆる職権特例判事補の指名を受けて判事と同一の権限行使が可能になるが,現実に地方裁判所の訴訟事件を単独で担当するかどうかは,配置された裁判所の裁判官の構成にもよる。特例判事補の期間には,行政省庁へ出向する者,局付になる者等がいるほか,少数ながら高等裁判所の職務代行を命じられて,控訴事件の陪席裁判官を経験する者もいる。
(2) 本人の同意等
裁判官の異動については,転所に関する保障(裁判所法48条)があるので,すべて本人の同意の下に行われている。異動に関する基本資料として,毎年,全裁判官が裁判官第二カード(なお,裁判官第一カードは,履歴書の簡略版である。)により,勤務地と担当事務について希望を提出している。勤務地の希望は,圧倒的に首都圏が多く(7割前後は首都圏希望ではないかと思われる。),そのほかは京阪神地域の希望も相当数ある。このように,勤務地の希望が偏っていることから,希望者の多い大規模庁に転入する判事10年目くらいまでの者については,機会均等を図るため,「何年後には最高裁の指定する庁に転出する」という約束(あくまで紳士協定的なもの)を書面でする扱いとなっている。
(3)
判事補については,できるだけ幅広い経験を積めるように,大・中・小という規模の違う裁判所を回るよう配慮されているが,空きポストその他の関係から,例外なしに実行できているというわけではない。判事補時代から判事なりたての時期ころまでは,新任の期間(前述のように2年半。)を除き,3年単位で異動するが,その後は4,5年間隔の異動が増え,特に地方裁判所・家庭裁判所の部総括については,裁判長が頻繁に交代するのを避けるため,5年の在任を原則としている。また,判事任命後10年以上経つと,次第にほぼ同一高等裁判所管内の異動に落ち着いてくる。
簡易裁判所判事については,任命後最初の異動と,人によってもう1回くらい遠隔地の簡易裁判所に行ってもらうほかは,概ね出身高等裁判所管内で異動している。異動のローテーションは3ないし5年間隔である。
(4) 異動案の作成等
異動の大部分は,所長等の人事を除き,毎年4月期に定期異動として実施される。異動計画の原案は,高等裁判所管内の異動については主として各高等裁判所が,全国単位の異動については最高裁判所事務総局人事局が立案し,いずれについても最高裁判所と各高等裁判所との協議を経て異動計画案が作成される。異動の内示は,事件処理と住居移転の関係を考慮して,原則として異動の2か月以上前に,離島などについては3か月以上前に行われ,承諾があれば,最高裁判所裁判官会議の決定を経て発令され,承諾がない場合には,異動先の変更が行われたり,留任の取扱いがなされる。
異動案は,各裁判所でどのような経験等を持つ裁判官が何人必要かという補充の必要性,任地・担当事務についての各裁判官 の希望,本人・家族の健康状態,家庭事情等を考慮し,適材適所・公平を旨として立案される。適材適所・公平といった面で,人事評価が影響することになる が,少なくとも所長等への任命以外の一般の異動に関する限り,実際には,上記の人事評価以外の事情が影響する度合いが高い。特に近年は,配偶者が東京等で 職業を持つ割合が格段に高くなったこと,子弟の教育を子供の幼いうちから東京等で受けさせるために比較的若いうちから地方へ単身赴任する者が増えたこと, 親等の介護の必要から任地に制限を受ける者が増えたことなどから,家庭事情に基づく任地希望が強まっている。現に,首都圏や京阪神地域の裁判所において, こうした事情を抱える裁判官は相当数に上る。また,判事補や若手の判事については,幅広い経験ができるように,評価とかかわりなしに大規模庁に異動するこ ともある。したがって,若手のうちは,異動において人事評価が影響する程度は,限定されたものである。
5. 昇給の実情
(1) 裁判官の給与体系
裁判官の給与体系については,裁判官の報酬等に関する法律に定められており,報酬については,判事補は12号から1号までの12の,また,判事は8号か ら1号及びいわゆる特号まで9の刻みとなっている。簡易裁判所判事については,17号から1号及び特号までの18の刻みとなっている。
現在の報 酬制度については,号の刻みが細かすぎて,裁判官の職務にふさわしくないのではないかという議論が従来からあるが,裁判官といえども次第に経験を積んでよ り責任の重いポストに就いていくという面があり,判事の場合であれば,10年から30数年までの経験差とそれに応じた職務の差があるので,相当数の段階は設けざるを得ないという考え方に基づくものである。また,社会全般に年功序列型賃金が行われてきた中で,一般公務員の給与体系の上に,これと連動した形で報酬額を定めることによって,報酬のレベルが確保されるとともに,社会的実情に則した報酬体系となっていたともいえる。この点については,審議会意見において,「裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,現在の報酬の段階の簡素化を含め,その在り方について検討すべきである。」と指摘されており,今後検討すべき課題となっている。
裁判官の報酬は,一般公務員のそれよりも高い水準にあるが,それは,裁判官の地位,職責の重要性や,超過勤務手当が支給されず,その分が報酬に組み入れられていることなどによる。
(2) 昇給の実情
以上のように細かい刻みで昇給していくことが,裁判官の独立に影響してはならないことはいうまでもないことであり,任官後,判事4号まで(法曹資格取得 後約20年間)は,長期病休等の特別な事情がない限り,昇給ペースに差を設けていない。判事3号から上への昇給は,ポスト,評価,勤務状態等を考慮し,各高等裁判所の意見を聞いた上,最高裁判所裁判官会議において決定されている。
6.人事評価の現状
(1) 人事評価の根拠
国家公務員の一般職については,後記(第3・1(1))のとおり,国家公務員法(72条)に基づく勤務評定制度があるが,裁判官については,法令に基づ く制度としての勤務評定制度はない。しかし,多数の裁判官について配置等を決定する必要がある以上,人事評価の必要性は否定し難いので,これまで運用とし て,裁判官の人事評価に関する資料を収集することが行われてきた。
(2) 人事評価に関する基本的な情報(報告書)
現在,裁判官の人事評価に関する基本的な情報となっているのは,毎年1回,高等裁判所長官及び地方裁判所長・家庭裁判所長が所属の裁判官について作成 し,最高裁判所に送付している報告書である。この報告書は,様式があるわけではなく,裁判官の仕事振り,力量,人物,健康状態等について,自由に記載したものであるが,各裁判官の裁判官第二カード(前記4(2)参照)の提出に合わせて,ほぼ同じころ作成される。
平成10年までは,「平成10年ま で用いられてきた書式」に示すように,「事件処理能力」(正確性,速度,法廷の処理),「指導能力」(職員に対する指導,部の総括者としての適否),「法律知識及び教養」,「健康」,「人物性格の特徴」,「総合判定」という項目を設けた書式が用いられていた。
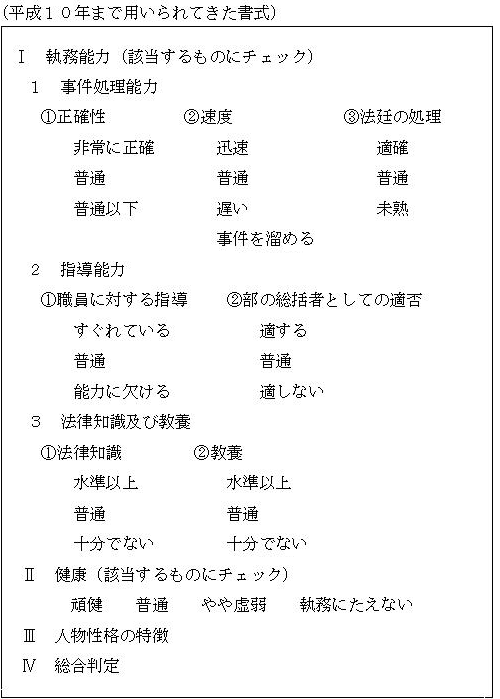
この書式が廃止された理由は,こうした項目自体が不適切ということでは必ずしもない。この書式では,掲げられた項目に関する一定の評価文言をチェックするという方式が主体になっているために,どうしても評価の視点が固定的になりがちで,人物性格の特徴の記載なども平板なものになって,その裁判官の特徴が浮かび上がってこない場合が多かった。そこで,むしろ,項目にこだわらず,対象となる裁判官の担当事務,経験,個性等に応じて,文章により,適切な表現を用いて自由に記載してもらう方が,その裁判官の適性等がより具体的に把握できるのではないかというのが,方式変更の理由である。
実際にも,自由 記載方式にしたことにより,従来に比べれば,紋切り型の平板なものが減り,より具体性のある評価が増えてきている。自由記載方式の場合,どういう項目について,いかなる観点から評価すべきかが不明ではないか,評価の客観性・公平性が保たれないのではないかといった点が問題になる。しかし,従来の書式に掲げ られたような項目が,裁判官の人事評価に当たって問題となる基本的な事項であることは言うまでもない。評価者である高等裁判所長官や地方裁判所長・家庭裁判所長は,裁判官としての長い経験を有する人たちであるから,その点を含め,裁判官の力量,実績をどのような観点から評価すべきかということについて,相当程度一致した理解を有している。さらに,初めて所長になったような場合には,前記報告書の趣旨や記載内容等に関する説明も行っている。もちろん,評価者によって評価の観点や求めるレベルがある程度異なることは避けられないが,次に述べる人事評価の目的等の面から考える限り,その点は評価の効用を大きく損なうものではないと言いうるし,また,この問題は人事評価には常に伴うことでもある。これまでの人事評価においては,長い期間を掛け,たくさんの人が見ることにより,評価の客観性・公平性が保たれるという考え方がとられてきた。
ところで,従来の書式に掲げられた項目自体,かなり概括的なものであり,現在は全く不定型な評価になっている。このようなもので足りるとされているのは,前述のように,人事評価が給与に影響するのは経験年数の長い一部の裁 判官に限られること,異動についてもその影響は限定的であること等から,勤務評定が毎期の勤勉手当や賞与の額に影響する一般職公務員や民間会社と異なり, 毎期ごとの明確なランク付けは必要がなく,適材適所の配置をするために,当該裁判官がいかなる適性を有するのかを知ることが主体でよいからである。これに加え,特に判事補を始めとする若手の裁判官については,当該裁判官の長所短所を知り,今後の指導に役立てるという観点も重視されている。
(3) 報告書作成のための資料等
高等裁判所長官や地方裁判所長・家庭裁判所長が,どのような調査や資料に基づいて,報告書を作成するかという点であるが,多くの裁判所においては,所属する裁判官はそれほどの数ではないので,長官,所長は各裁判官と接触する機会が相当程度あり,裁判官の仕事振り,力量,人物,健康状態等について,直接知る機会がある(大規模な裁判所においては,所長代行が所長を補佐している)。その他に,陪席裁判官については,部総括から話を聞くことが多いであろう。逆に,部総括に関する話を同じ部の陪席裁判官や職員から聞くということもあろう。裁判官の力量や適性は,同じ事件を担当したり,一緒に仕事をしてみると,よくわかるという面がある。その点では,次に述べる上級審裁判官も同様である。こうした形で仕事を通じて本人の力量等を知る裁判官の数は,長い間には相当の数に上る。その評価の集積により,その裁判官の評価が固まってくるのであって,この評価には相当の信頼性があると考えられる。高等裁判所長官,地方裁判所長・家庭裁判所長の評価も,こうした裁判官の中での評価を踏まえている。
以上に述べたもの以外にも,人事評価に関連した情報は存在する。例えば,高等裁判所の裁判長等からは,多くの上訴事件の判決と記録を通して見た下級審裁判官の仕事振りや力量についての情報がもたらされることがある。もっとも,こうした情報は,全ての裁判官について,逐一,網羅的に調査しているものではなく,良否いずれにせよ,目に付くケースについて,人事担当者に伝えられることがあるというものである。
なお,仕事振りという点に関し,事件の処理件数が最大の基準であると言われることがある。裁判官として,適切な期間内に事件を処理することが要請されており,審理が終結しているのに,何時までも判決を書かずに事件を溜めるというようなことがあれば,それは問題になる。しかし,処理件数が多くても,審理や判決が粗雑であれば高い評価を受けることはなく,反対に,処理件数は少な目でも,古い難しい事件の判決をした場合や,判決の内容が素晴らしい場合等は,高い評価を受ける。ただし,判決の内容が問題になるといっても,事案を正確に捉えているか,理由の記載が行き届いているかといった判決の水準を問題とするのであって,有罪か無罪か,国を勝たせたかどうかといった,結論の当否を問題とするわけではない。なお,各裁判官の事件処理数を記載した一覧表のようなものは,最高裁判所に報告されていない。
